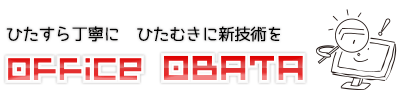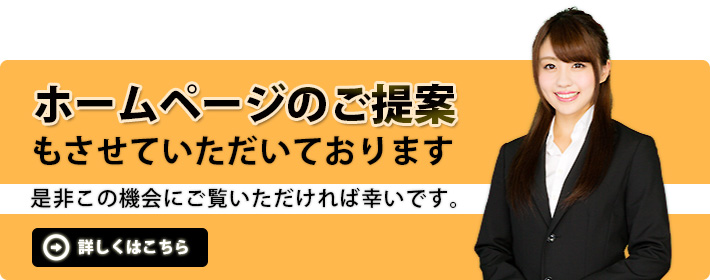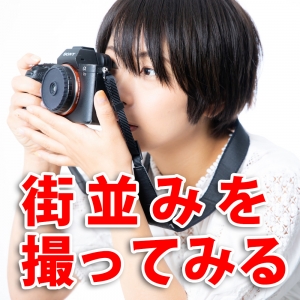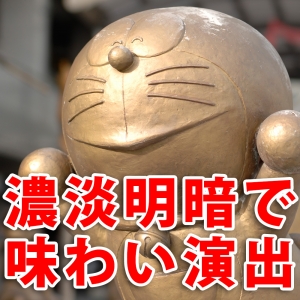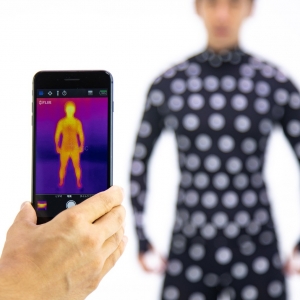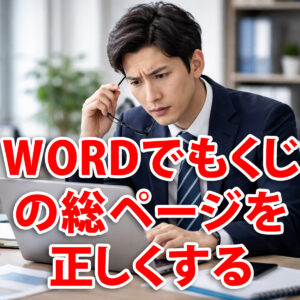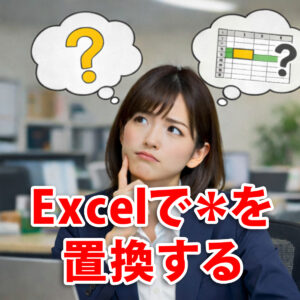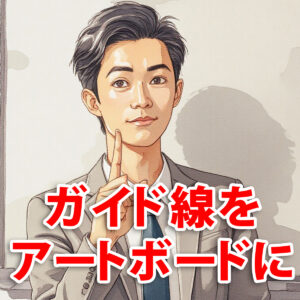尾山神社を撮ってみた。
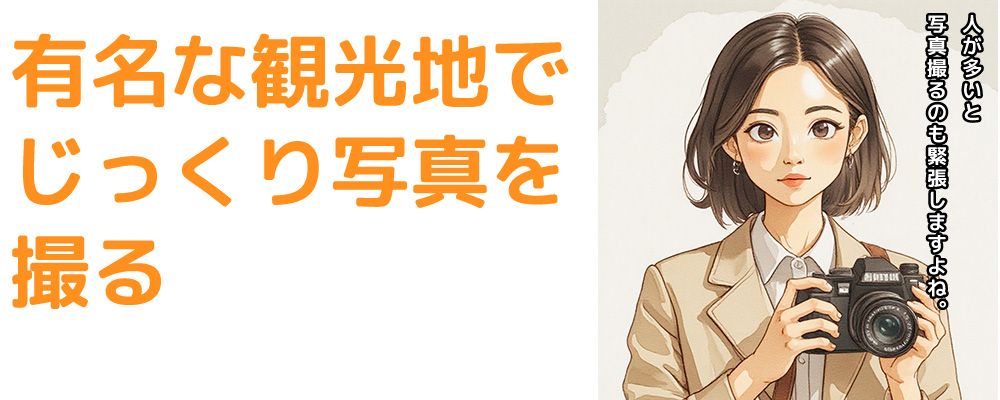
ロケ写真は、撮影者の好みがでます。
例えば朝日や、夕景などの1日の時間の変わり目であったり、夜のライトアップであったりなどです。
ちなみに私は、「青空」を好んで撮影します。
撮影タイミングが長いことと、朝早起きしなくてもよいところが良い点です。
というわけで、今回は有名観光地で写真を撮ってきました。
今回の撮影地は「尾山神社」

今回は澄み渡る秋晴れの中、尾山神社を撮影しました。
以前から、金沢付近の撮影に行ってみたいと思っていましたが、コロナの時期は自重していたこともあり、ようやく遠出しての撮影ができるようになったこともあります。
尾山神社は人が多い。
これまでは、近くの撮影スポットを撮影してきましたが、特色として「人がほとんどいない」場所でした。
そのため、あまり気にしませんでしたが、今回は「人が多い場所での撮影」でした。
大きいカメラを抱えながらの撮影は、思いのほか人の目が気になりました。
有名観光地撮影の場合は、必ず起こることです。
そんなかでの撮影でした。
まずは境内正面

尾山神社独特の西洋っぽい門をくぐると、境内が見えます。
いかにもという感じで境内が見えます。
左右傾き防止テクニックを駆使し、水平になるように撮影します。
ちなみにここに来るのは、中学生の時以来だと思います。
お松様の石碑

境内を正面に見て、右手側にお松様の石碑がありました。
観光ガイド系のサイトでは、正面写真が多いですが、石碑のお松様は左側を向いておられます。
なので、「何かを見つめている感」が醸し出るようなイメージで撮ってみました。
利家公の像

お松様の石碑の先には、利家公の銅像がありました。
比較的高い台座の上にあり、こういった場合は「青空背景」で撮影します。
天気が良いと、青空写真がとてもよく映えます。
先ほどのお松様の石碑は、利家公を見つめるように設置されていたようです。
有名な庭園の橋

利家公の銅像からさらに奥へ進むと、庭園がありました。
その中に、観光ガイドによく掲載されている橋がありました。
有名どころは自分なりに撮影し、他の作品と比較してみる。
比較すると、自分の至らない部分がよくわかります。

この橋は「渡ってはいけません」となっており、橋の上には苔が橋を着色していました。
彩度を抑えてみると、ひっそり感がでます。
謎の石

きれいに正方形にくりぬかれた石がありました。
医師の周りには苔が根付いており、加工されてから長い年月が経っていることがわかります。
自然の中に、加工物が混ざると、不思議な感じがします。
物静かな庭園と灯篭

絶妙なバランスで立っている感じのする灯篭が、なんとも味がありました。
境内側面

レンガの塀は、明治時代になってから作られたものだそうですが、それでも100年以上前のものです。
そんなレンガ塀の向こうに見える、日本古来の境内との組み合わせが、なんとも不思議な感じがしました。
利家公の兜(レプリカ)

境内側に戻ってくると、利家公の兜を模したレプリカの兜がありました。
正面から撮影すると、境内が背景になるように撮れます。
背景ぼかしをするか、しないかで悩みましたが、背景ぼかしで撮ってみました。
独創的な狛犬

尾山神社の狛犬は、独創的ということでも有名です。
狛犬ではあるのですが、体つきがスマートで前足が長いです。
順光状態でしたので、綺麗に撮れました。

反対側の狛犬です。
こちらは反逆光状態であったため、少し暗いですが、構図的にはこちらのほうが絵になります。
人の多い場所での撮影は、被写体に夢中になるとうまく撮れます。
今回は、人の多い場所での撮影で、周囲の目が気になる場合は集中力がそがれがちです。
ですが、ファインダーの向こうの被写体に集中し、ひたすら絵になる構図を探すと、人の目も気にならなくなります。
せっかくのロケーションならば、被写体に夢中になるほうが、良い写真が撮れます。
撮影技術に関する記事を以下にまとめています。
またご参考になれば幸いです。