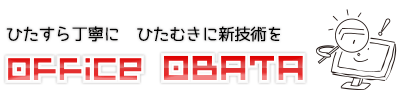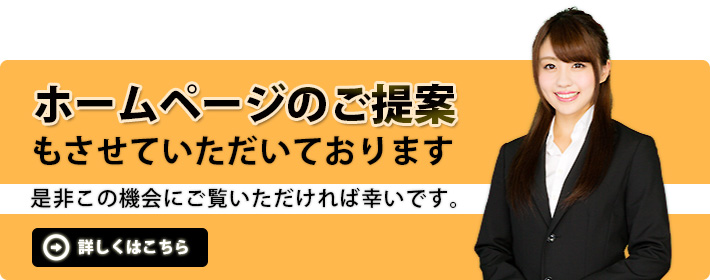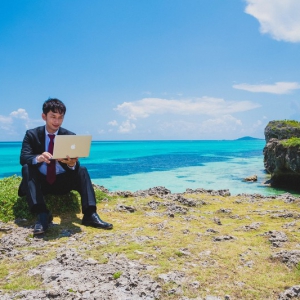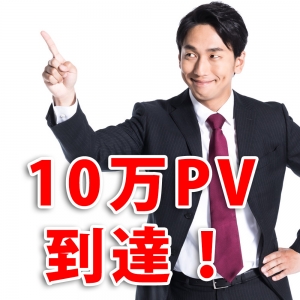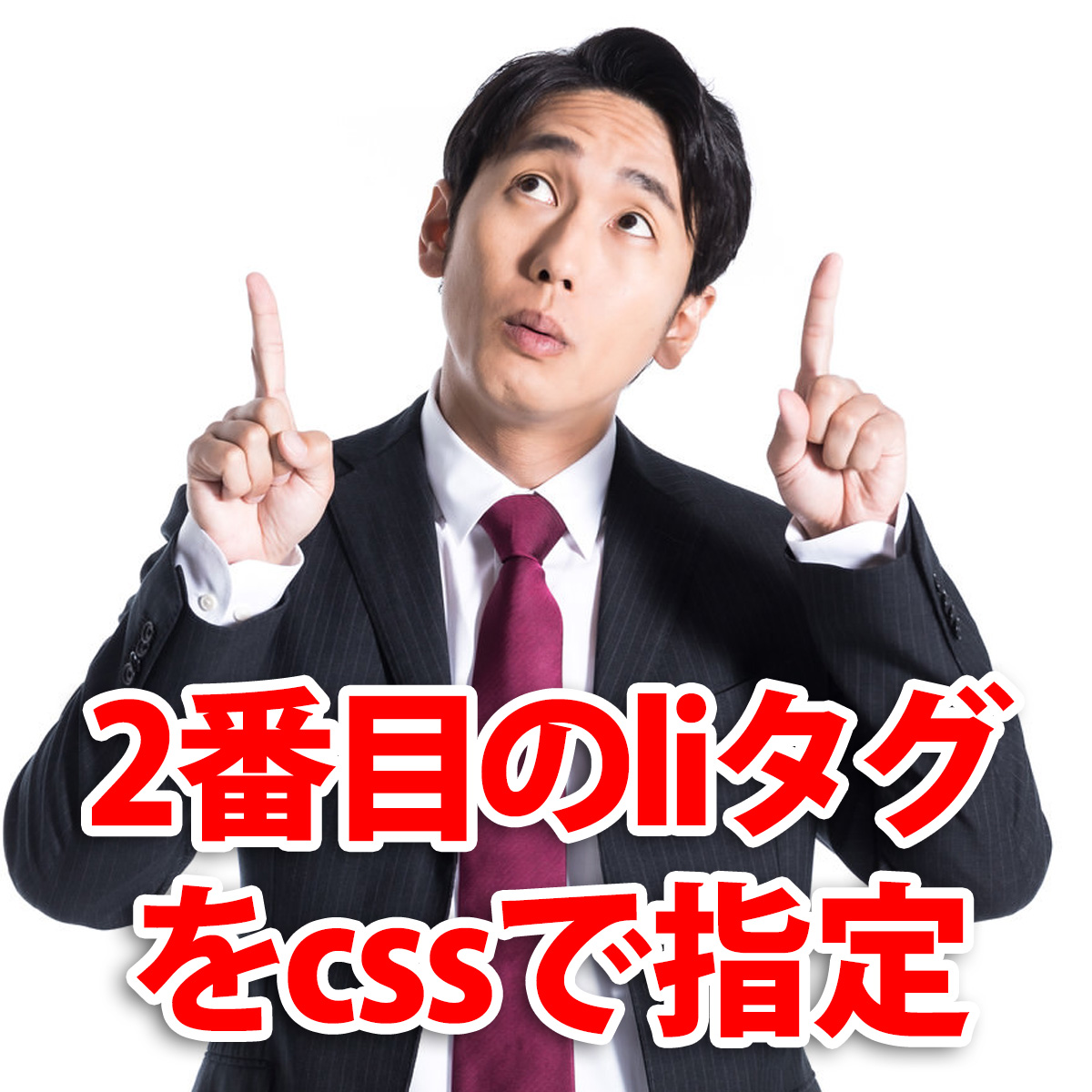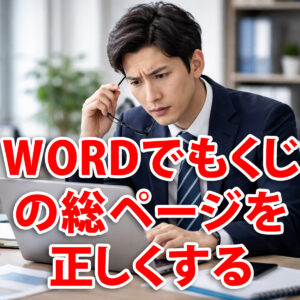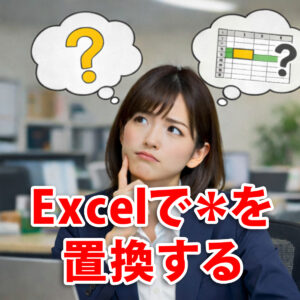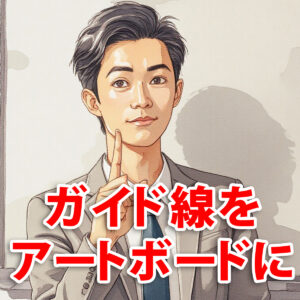いまさらながらマイナンバーカードを申請しマイナ免許証をつくってみた。
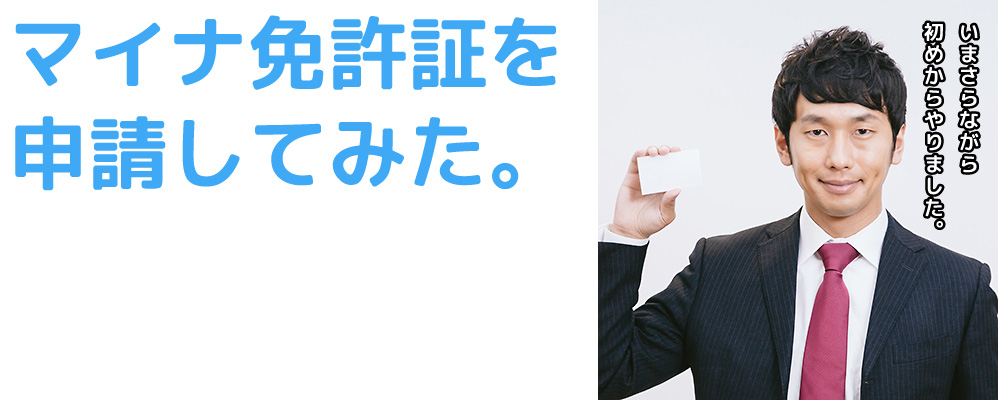
マイナンバーカードが導入されてからしばらく経ちましたが、ようやくマイナンバーカードを申請しました。
いままで申請しなかったのはひとえに以下の理由からです。
- 免許証とマイナンバーカードが一体化したら申請しよう。
いずれ免許証と一体化すれば、いろいろと手間が減るだろうと思いずっと待っておりました。
ようやく免許証とマイナンバーカードが一体化したので、申請しようと思い立った次第です。
ところが、思わぬ落とし穴がいくつかあったので、体験談として記録いたします。
思わぬ落とし穴(1)免許証と一体化するにはマイナンバーカードを持参しなければいけない
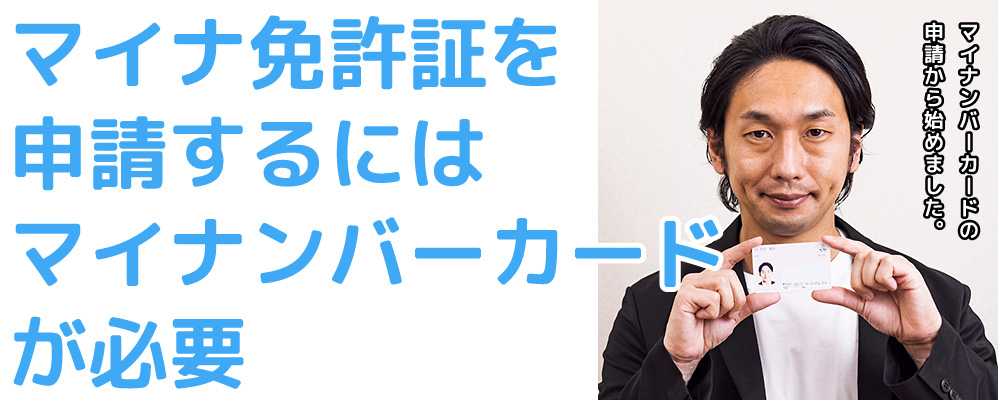
免許証一体化マイナンバーカードは、免許更新センター等に申請すれば、初めからマイナンバーカードと一体化状態で発行されると思い込んでいました。
ですがいざ調べてみると違っていました。
正確には、
マイナンバーカードを持参して、免許更新センター等で申請する
でした。
つまり、マイナンバーカードを持っていない場合免許一体型マイナンバーカードは申請できません。そのため私は、以下の手順を踏む必要がありました。
- マイナンバーカードを申請して交付してもらう
- マイナンバーカードを持って、免許更新センター等でマイナ免許証を申請する
何でもかんでも1枚にまとめるためには、各機関に出向いてその都度申請しないといけないということでした。
ということで、まずはマイナンバーカードを申請することにしました。
思わぬ落とし穴(2)マイナンバーカードを申請するためには「申請書ID」が必要
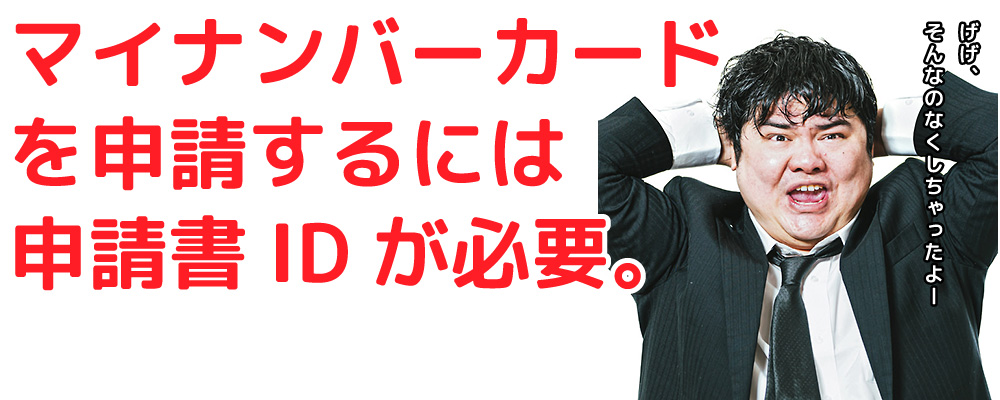
マイナンバーカードは持っていませんが、自分のマイナンバーはわかります。
マイナンバーカードの取得はインターネットから申請できるので、簡単にできるだろうと思っていました。
いざやってみると次ところで手が止まってしまいました。
「申請書IDを入力してください。」ただしマイナンバーは入力しないでください。申請書IDは郵送された書類に記載されています。
なんですと?
申請書IDなんてわかりません。
申請書類は確かに昔来ていたと思いますが、マイナンバーだけ大事にしまっており、申請書IDの書かれた書類は紛失状態です。
申請書IDがない限り、申請はできません。
どうしたらよいか調べてみると、以下の2種類の方法がありました。
- 郵送で申請(手書き書面にて申請する)
- 市役所で申請書を再発行してもらう
私はインターネット申請で済ませたいと考えています。
手書き申請はしたくありません。
ということで、市役所で申請書を再発行してもらうことにしました。
申請書の再発行は10分ほどでできました。
早速市役所へ行き、窓口で「マイナンバーカード申請書を紛失しました。」「大変申し訳ないですがマイナンバーカード申請書の再発行をお願いいたします。」と伝えました。
その際に以下のものを提出しました。
- 免許証
- マイナンバーがわかる書類の写し
少々お待ちくださいと言われ、10分ほど待って申請書と合わせて、提出した免許証、マイナンバーの写しを返却していただけました。
これでマイナンバーカードを申請する準備が整いました。
いざインターネットからマイナンバーカードを申請しました
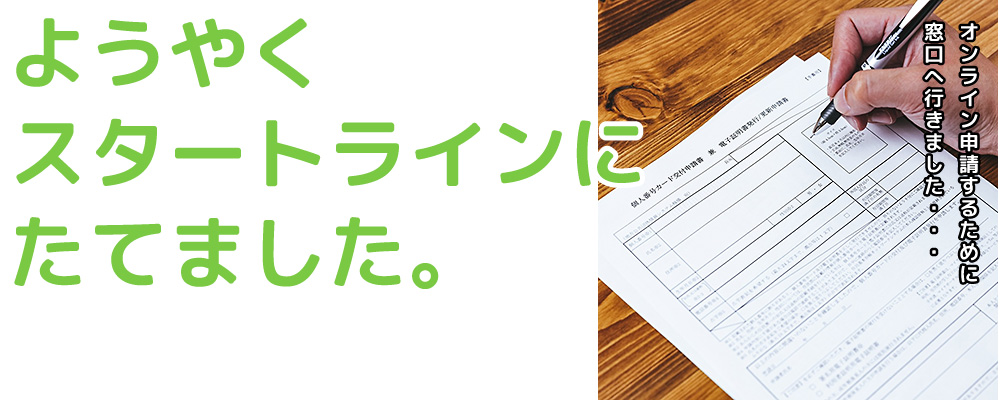
インターネットからマイナンバーカードを申請するには以下のものが必要です。
- 自分の写真(スマホ等で撮影したものでOK)
- メールアドレス
自撮りでOKなのはありがたいです。
ただ免許証同様何年も使われる写真ならば、散髪してからにしようと思い、理容院に行ってからスマホで自分の写真を撮りました。
申請書IDと写真が用意できたので、マイナンバーポータルサイトからオンライン申請を行いました。
といっても、3分ほどで終わりました。
必要事項を入力し、メールアドレスの確認を行い、写真を投稿して終わりました。
あとは、マイナンバーカードが届くのを待つのみです。
マイナンバーカード受け取り
インターネットでマイナンバーカードを申請してから20日ほどして、受け取り案内のはがきが届きました。
はがきには、記載されている場所へ行って受け取りをしてくださいと書かれていました。
マイナンバーカード受け取り時に必要なものは以下の通りです。
- 受け取り案内通知はがき
- 免許証(身分証明書)
- マイナンバーが記載された紙のカード
この時、パスワードを設定してくださいと言われました。
16桁以内の英数字と、数字4桁のパスワードです。
自分で直接入力する方式なので、他の方からは見えない仕様になっています。
またインターネット(マイナポータルサイト)からパスワードを変更することもできました。
マイナンバーカードにおいて、パスワードは結構重要なセキュリティなので、交付窓口でパスワードが漏れるのではないか不安になる場合は、家に帰って速攻でパスワードを変更するのもありです。
保険証との連携
マイナンバーカードが届いた段階では、保険証は連携していません。
自分で手続きしないとできないのです。
というわけで、保険証との連携方法調べてみました。
インターネットで保険証を登録するには、マイナンバーカードを使ってマイナポータルサイトにログインする必要があります。
ログイン方法は主に以下のやり方があります。
- スマホにマイナポータルアプリを入れてログインする
- パソコンにカードリーダーをつけて、マイナンバーカードを読み取ってログインする
マイナポータルサイトから、保険証との連携を選択し、言われるままボタンを押していったらあっさり連携できました。マイナポータルサイトから申請し、10分ほどでマイナンバーカードが保険証代わりになりました。
このとき、旧保険証の番号等は必要ありませんでした。
おもいのほかあっさり保険証との連携ができました。
思わぬ落とし穴(3)スマホがマイナポータルアプリに非対応
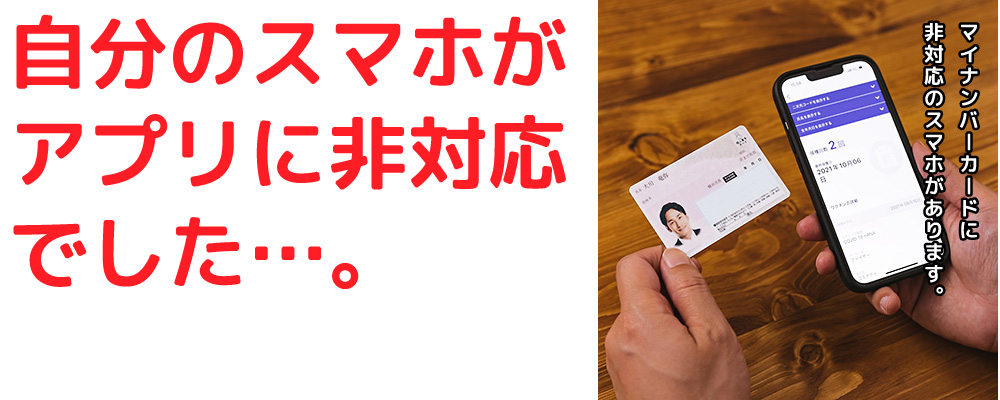
スマホを使うのが簡単だと思い、スマホにマイナポータルアプリをインストールしようとしたところ、
お使いのスマホは本アプリに対応していません。
と表示されました。
カードの読み取り機能が付いていないスマホだと駄目のようです。
ということで、PCからカードリーダーを使ってログインすることにしました。
まずはカードリーダーを手に入れる
マイナンバーカードに保険証を紐付けるためには、マイナポータルサイトから申請する必要があります。
マイナポータルサイトへログインするためには、私の場合PCからマイナンバーカードを読み取る必要があります。
PCからマイナンバーカードを読み取るためには、カードリーダーが必要です。
ということで、カードリーダーを買いに電気屋さんへ行きました。
ところが私の住んでいるところは田舎のせいか、どの電気屋さんにもカードリーダーが置いてありませんでした。もしかしたら、スマホが普及しPCでマイナンバーを読み取ること自体需要が少ないのかもしれません。
店舗にない場合はネットで購入。
amazonで以下の商品を購入しました。
ソニー(SONY) 日本製 ソニー 非接触ICカードリーダー/ライター PaSoRi RC-S300
カードリーダーはamazonにたくさんありましたが以下の理由でsonyのものにしました。
- 非接触型のものが欲しかった
- 実績のあるメーカーのほうが安心できる
- 値段も適正価格(安すぎるとなんだか不安)
実をいうと、10数年前にPCでEDY決済をするために、EDYカードをパソコンで読み取れるSONY製のリーダーを購入していたのですが、いまだに故障せず使えています。そんなこともあり、SONY製なら問題ないだろうとおもいました。
いよいよ本命のマイナ免許証を申請する
マイナンバーカードを手に入れ、保険証と連携し、マイナポータルサイトであれこれ設定したら、いよいよ免許証との連携です。
マイナポータルサイトには、色んな省庁との連携(厚生労働省、国税局など)申請する部分があり、その中に「マイナ免許証連携」というものがありました。
早速やってみたところ、連携失敗となりました。
どうやら、免許証との連携には、免許センター等で手続きする必要がありました。
マイナ免許証の申請ができる場所
ここで疑問がわきました。
マイナ免許証の申請は、どこでやればいいの?
警察署?免許更新センター?
色々調べていたら、富山県の場合は以下のホームページに書かれていました。
当初は、富山県で1ヵ所しかない「運転教育センター」だけでしか受付していませんでしたが、各市町村の警察署でもマイナ免許証申請ができるようになっていました。
運転教育センターは少し遠いので、近くで申請できるのはありがたいです。
マイナ免許証申請に必要なもの
マイナ免許証申請に必要なものは以下の通りです。
- 現在の運転免許証
- マイナンバーカード
- 手数料(初めての場合 1,500円)
- マイナンバーカードの暗証番号(16桁の番号)
16桁の暗証番号を覚えていない場合は、後日富山県に1ヵ所しかない運転教育センターへ行き、最終手続きをしてくださいとのことでした。
16桁の暗証番号がわかっていれば、警察署で最終手続きが完了します。
2枚持ちにするかどうか
マイナ免許証を申請する際に、以下の2つから選ぶことができます。
- 従来の免許証を廃棄しマイナ免許証に一本化する
- 従来の免許証とマイナ免許証両方持つ
ちなみに手数料は同じです。
私は2枚もちにしました。
理由としては、従来の免許証がないと利用できない民間サービスがあるからです。
例えばレンタカーなどのサービスは、従来の免許証がないと車を借りることができません。
理由は、レンタカーの店舗でマイナ免許証を確認する機械が導入されていないためです。
他にも身分証明として免許証のコピーを取るケースもあります。
そういった場合に、従来の免許証がないとサービスが受けられない可能性があります。
そういう意味で2枚持ちのほうが、よいと思いました。
いずれ、民間サービスでもマイナ免許証に対応できるようになったら、一本化で良いように思います。
ちなみに2枚持ちの場合、従来の運転免許証かマイナ免許証のどちらかを持っていれば、免許不携帯にならないということでした。
いざマイナ免許証を申請してみました
私は市内の警察署でマイナ免許証の申請を行いました。
警察署窓口で「マイナ免許証の申請をお願いします」と伝えると、窓口の方が親切に応対してくれました。
免許証とマイナンバーカードを提出し、書類に必要事項を記入しました。
その後、マイナンバーカードに登録された免許証の情報に誤りがないか、確認します。
もし間違いがあったら、いろいろ面倒なことになると思い、念入りに確認しました。
マイナンバーカードに登録された内容が間違いないことを確認したら、1,500円の収入印紙を購入し、書類に張り提出しました。
最後に、マイナ免許証登録の電子申請を行う必要があるとのことでした。
この時に、16桁の暗証番号を自分で入力します。
もし、16桁の暗証番号がわからない場合は、後日富山県に1ヵ所しかない、運転教育センターへ行って電子申請する必要があるとのことでした。
私は暗証番号を覚えていたので、警察署で電子申請ができ手続きをすべて終えることができました。
この間約20分ほどでした。
最後にマイナポータルサイトから「連携」を行う

警察署で一通り申請手続き、電子申請手続きができたら、自宅からマイナポータルサイトにログインし、マイナ免許証の連携を設定します。
警察署の話だと、申請してから中央のサーバーへ反映されるまでしばらく時間がかかるため、マイナポータルからの連携はしばらく待ってからやってくださいとのことでした。
ちなみに私は、警察署での申請後1時間ほど過ぎたころにやってみたところ、連携できました。
これで、マイナ免許証の完成です。
各種情報が一本化できるのは便利ですが、そこにたどりつくまでの道のりが波乱万丈でした。